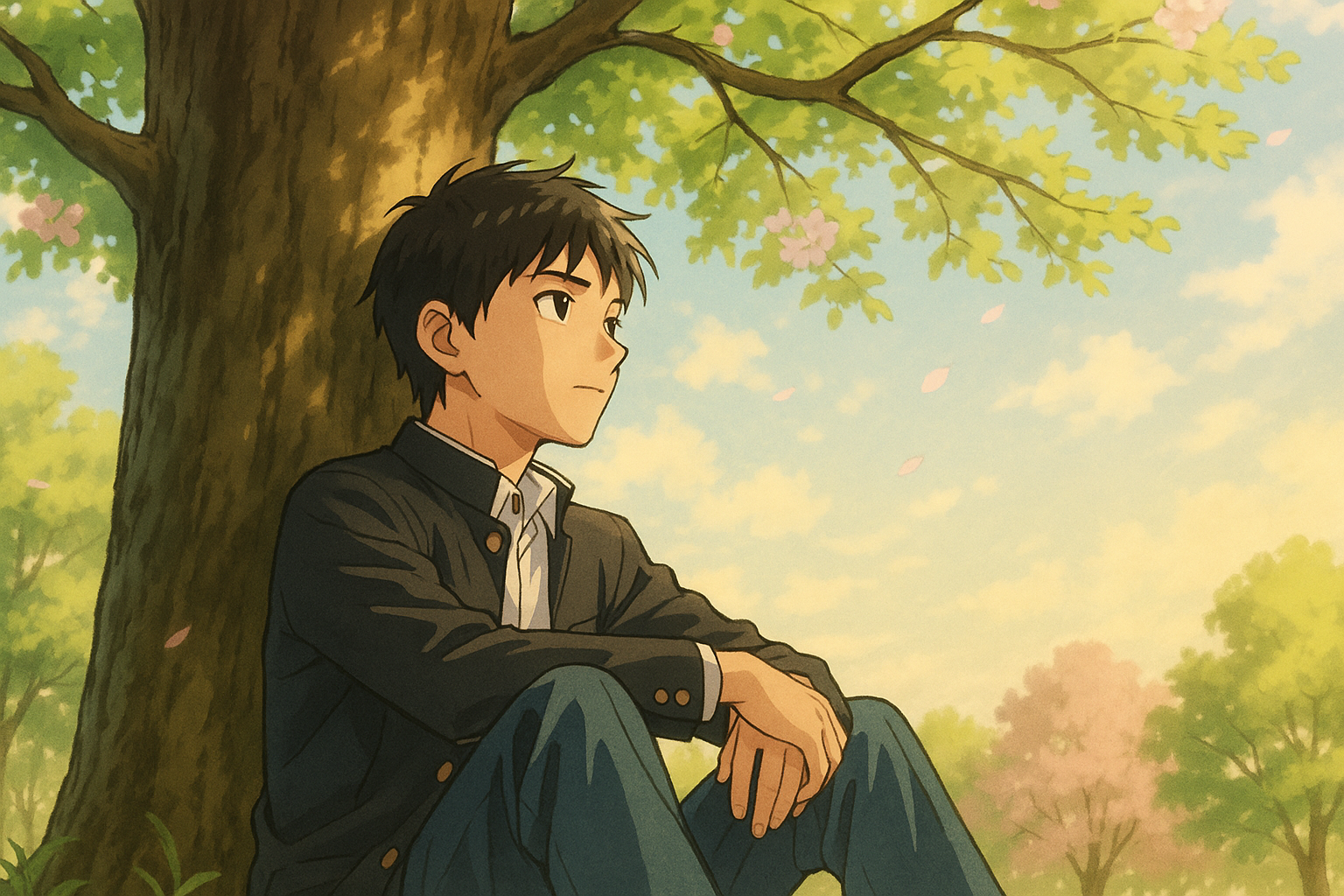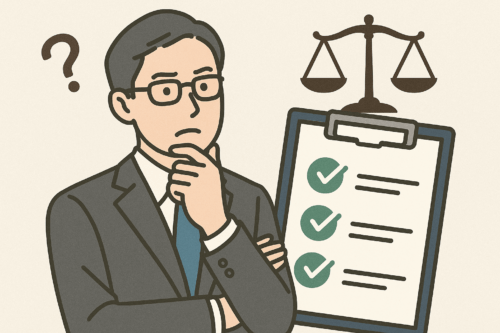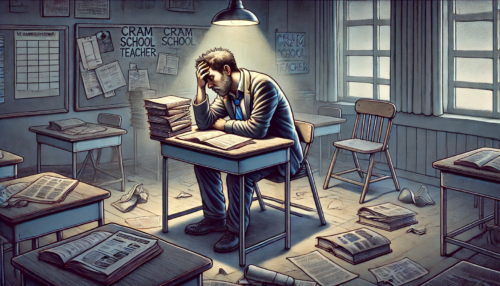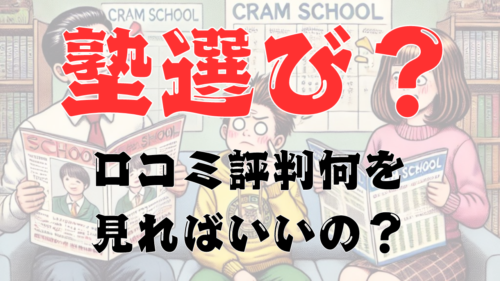学習塾経営には“ぶれない柱”と“柔らかな枝”が必要
1. なぜ塾は同じ経営方針でも成功と失敗に分かれるのか?
私が塾を始めたころ、近くに同時期に開業した塾がありました。
条件はほぼ同じ。立地も悪くないし、指導経験も豊富な先生がやっている。
それなのに、2年後、その塾は閉じてしまいました。
「何が違ったのか?」
私はその答えをずっと考え続けました。
そして気づいたのです。
長く続く塾には、必ず“ぶれない柱”と“柔らかな枝”があるということに。
2. “ぶれない柱”がない塾は、なぜ迷走するのか?
“ぶれない柱”とは、塾の理念や信念。
私の塾の場合は、
- 短期間の点数アップよりも、長期的な学力の土台をつくる
- 一人ひとりの学習習慣を育てることを優先する
この二つは絶対に譲らない、と決めています。
でも、柱がないと何が起きるのか。
それは、生徒や保護者からの要望にすべて応えようとする“迎合”です。
「宿題を減らしてほしい」「テスト前だけ通わせたい」
こうした声をそのまま受け入れてしまえば、一見喜ばれるようでいて、指導の一貫性は崩れていきます。
やがて「この塾は何を大事にしているのか分からない」となり、信頼を失ってしまうのです。
3. 時代や地域に合わせて姿を変える“柔らかな枝”
とはいえ、柱だけが強くてもダメです。
時代や地域の変化に応じて枝を伸ばす柔軟さ。これがない塾は、気づけば時代遅れになります。
私も最初は紙教材だけでやっていました。
しかし、部活動の時間が遅くなり、自宅での予習復習時間が減っていく現実を目の当たりにしました。
そこでオンライン教材や家庭学習アプリを導入。
保護者との連絡も、電話や紙のお知らせからLINEに切り替えました。
これにより、生徒が通えない日でも学びを止めずに済むようになったのです。
この「方法を変える柔軟さ」が、“柔らかな枝”です。
4. バランスが崩れると塾はどうなる?
柱が弱すぎると、どんどん迎合し、塾は特色を失います。
枝が硬すぎると、変化に追いつけず、生徒のニーズとずれていきます。
私が見てきた中で、ある塾は「昔ながらのやり方」に固執しすぎていました。
生徒はスマホやタブレットで情報を得る時代。
それでも「プリントだけで十分」と言い続けた結果、保護者からは「柔軟性がない」と敬遠されてしまったのです。
大事なのは、両方を同時に育てること。
そのためには“地域性”への理解が欠かせません。
5. 地域に根差す塾こそ“枝”のしなやかさが命
地方の塾は、都市部以上に地域の生活リズムを意識しなければなりません。
私の塾がある登米市では、冬は暗くなるのが早く送迎時間が重要です。
部活の終了時間は学校ごとに違い、農繁期や地域行事があると生活リズムが一変します。
これらを無視して授業時間やスケジュールを固定してしまうと、「この塾は地域に合っていない」と思われてしまいます。
だからこそ私は、授業時間の調整や年間スケジュールの見直しを欠かしません。
それは枝を伸ばすように、地域の風を感じて形を変える作業です。
6. 土台を守る勇気――“やらないこと”を決める
柔軟さが大事と言っても、何でも受け入れるわけではありません。
理念を守るために、あえてやらないことも決めています。
例えば、値下げ競争には絶対に乗りません。
一時的に生徒は増えるかもしれませんが、長期的には「安さが売りの塾」というイメージがつき、指導の価値が軽く見られてしまいます。
また、全員の要望を反映させて教材や方法をコロコロ変えることもしません。
学習は積み重ねが命。そこを崩すような変化は、どれだけ要望があっても断ります。
7. 柱と枝が対話する経営
柱(理念)と枝(柔軟性)は、敵同士ではありません。
互いに支え合う関係です。
新しい取り組みを始めるとき、私は必ずこう自問します。
「これは理念に合っているか?」
「この方法は、今の生徒に合っているか?」
例えばオンライン質問アプリを導入したときも、便利さだけで選んだのではありません。
「生徒が自分で考え、解決の糸口をつかむためのサポートになるかどうか」を基準にしました。
こうして柱と枝の対話を続けることで、塾は少しずつ成長します。
8. 長く愛される塾の条件
長く続く塾は、「変わらない安心」と「変わる楽しさ」を同時に持っています。
保護者は「この塾は信頼できる」と感じる一方で、「毎年少しずつ良くなっている」と思えます。
授業の進め方は変えないけれど、教材やテスト対策プリントは常に最新。
面談の方針は変わらないけれど、説明資料はどんどん分かりやすくなる。
そうした進化を見せ続けることが、信頼を積み重ねる最良の方法だと私は思います。
おわりに
塾経営は、毎日の小さな判断の積み重ねです。
その判断を誤らないために、“ぶれない柱”と“柔らかな枝”を意識し続ける。
これは、どんな時代になっても変わらない経営の核心です。
次回は、この柱と枝のバランスを日々保つために、私が行っている“判断の基準づくり”についてお話しします。
それは、迷いをなくし、塾を安定して成長させるための大切な武器になります。