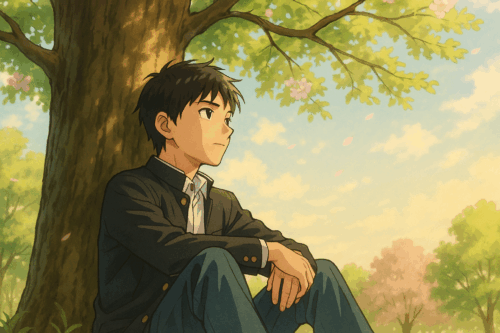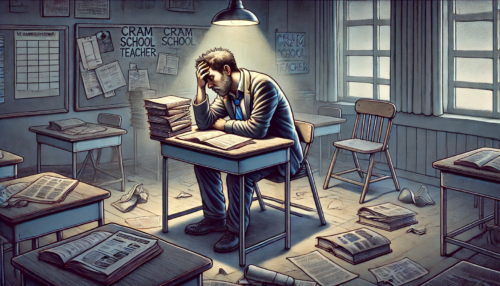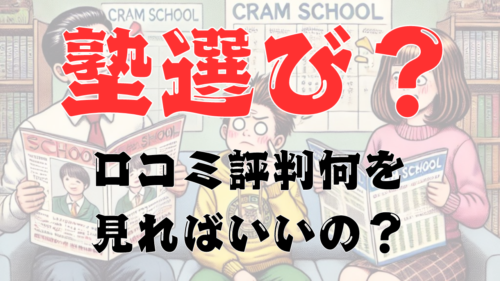塾を経営していると、毎日のように小さな選択を迫られます。
「この教材を導入するべきか」
「授業時間を変えるべきか」
「新しいコースを作るべきか」
一つひとつは些細に見えても、積み重なれば塾の未来を大きく変える決断です。
このとき、もし自分の中に“判断の基準”がなければ、決定は場当たり的になり、柱と枝のバランスが崩れてしまいます。
私が塾経営を始めて数年たった今、「判断の基準づくり」は迷いをなくし、塾を安定して成長させるための大切な武器だと痛感しています。
1. 判断の基準は“理念”と“現実”の間にある
柱(理念)と枝(柔軟性)を同時に守るためには、この二つの間に橋を架けるような基準が必要です。
私の場合、判断の出発点はまず理念に合致しているかです。
例えば、私の塾の理念のひとつは「生徒が自分で学ぶ力を育てる」こと。
だから、教材やシステムを選ぶときは必ずこう自問します。
「これは、生徒の自立学習を助けるだろうか?
それとも依存を生むだろうか?」
どれだけ便利そうでも、依存を助長するようなものは採用しません。
しかし現実的な運営面も無視はできません。
どれだけ理念に合っていても、予算や時間、人員の面で実現不可能なら、まずは代替案を考えます。
理念と現実――この両方を満たす案だけが「GO」のサインを得られるのです。
2. 判断をブレさせない「3つの質問」
日々の決断で迷ったとき、私は必ず次の3つの質問を自分に投げかけます。
- 理念に合っているか?
(塾の軸を壊さないか?) - 地域や生徒の現状に合っているか?
(今の環境にフィットしているか?) - 1年後も続けられる仕組みか?
(一時的な思いつきや流行ではないか?)
この3つすべてに「YES」と答えられたときだけ、新しい取り組みを始めます。
この基準を持ってから、決断が早くなり、迷いが減りました。
逆に、ひとつでも「NO」があれば、立ち止まって再検討します。
3. “枝”の判断は短期で、“柱”の判断は長期で考える
判断基準の中で特に意識しているのが、「時間軸の使い分け」です。
- 枝=柔軟な方法の部分は、3〜6か月単位で見直す
- 柱=理念や方針の部分は、最低でも3年単位で見直す
たとえば、テスト対策の方法や授業時間の設定は、学年の動向や学校行事に合わせて頻繁に改善します。
一方で「学習習慣を育てる」という方針は、3年経っても変えません。
こうすることで、短期の変化と長期の安定が両立します。
4. 感情だけで動かないための仕組み
塾経営は、人と人との関係が中心です。
だからこそ、感情に流されて判断してしまう危険があります。
「保護者が強く希望しているから」
「生徒が嫌がっているから」
――こうした理由だけで動くと、柱が揺らぎます。
私は感情だけで判断しないために、必ずデータと実例を確認します。
- 成績推移
- 出席率や学習時間
- 他の生徒への影響
これらを踏まえたうえで、最終的な判断を下すようにしています。
5. 判断の“保留”も立派な判断
判断基準を持つと、すぐに答えを出せることも多いのですが、それでも迷う場合があります。
そんなときは「保留」も選択肢に入れます。
一見後ろ向きに見えますが、情報が足りない状態での即決は危険です。
私は「次の定期テスト後に再検討」や「1か月試験運用」など、期限を区切った保留をよく使います。
これにより、柱を守りつつ、枝を試しに伸ばす余裕が生まれます。
6. 判断基準はスタッフとも共有する
塾が大きくなるにつれて、講師やスタッフとの連携が重要になります。
ここで判断基準を共有しておくと、スタッフも迷わず動けるようになります。
たとえば、「生徒が授業を休んだら、その日のうちに家庭連絡」というルールも、単なる業務指示ではなく、「学習習慣を途切れさせない」という理念から来ていることを説明します。
理由まで共有することで、スタッフは形だけでなく考え方まで理解し、同じ方向を向いて動けます。
7. 基準を持つことで得られる最大の効果
判断基準を持つことで得られる最大の効果は、「迷いによる疲弊がなくなる」ことです。
塾経営では決断の数が多く、ひとつひとつで悩んでいては心身が持ちません。
基準があれば、迷ったときも「この3つの質問に当てはまるか」で即答できる。
これが、安定した運営と着実な成長につながります。
おわりに
“ぶれない柱”と“柔らかな枝”を保ち続けるためには、その場の思いつきではなく、明確な判断基準が必要です。
理念と現実をつなぐ橋を持つこと。
短期と長期の時間軸を使い分けること。
感情に流されず、データと期限を味方にすること。
これらがそろって初めて、柱と枝は共に成長できます。